これまでの「ギターの選び方の話」では、アコースティックギターに使用されるさまざまな材料を特集して参りました。
(「ギターの選び方の話」その1 トップ材はこちらをクリック)
(「ギターの選び方の話」その2 サイドバック材はこちらをクリック)
今回はギターの選び方の話の第3弾です。
「ギターの設計について」考えてみたいと思います。
料理に例えますと、これまでの「素材」は「食材」に当たる部分でした。
今回の「設計」は「レシピ」に当たる部分だと思います。
素晴らしい料理には、どちらも欠かせませんね。
ギターも同じで、究極と言われるギターたちはやはりどちらも兼ね備えていると思います。
戦前の000-45 はまさにそんなギターでした。
逆に、、レシピを間違うと、高級食材を無駄にしてしまう、、なんていう可能性もあるのかもしれません。
アコギの世界でも、各種ブランドがいろんな設計(レシピ)を採用しています。
見た目はそっくりでも、音の設計は全く違うものもありますね。
また一眼見ただけでは、見えない部分での設計の差も音に大きく影響すると思います。
アコギというのはトップにかかる張力を大きく変えることができないと思います。
弦のゲージとレギュラーチューニングが決まっているからです。
もちろん弦を太くする、弦高を上げる、その他サドルやナットの角度や弦の貼り方などで多少は調整できると思います。
でも基本的にはかかる張力にかなり大きな差が出るということはないと思います。
それで弦が弾かれた時そのエネルギーを、どのように伝えるか、あるいはどのように増幅するか、という部分に設計の妙が出てくるのかもしれません。
振動を殺さないというのはもちろん、振動をコントロールしたり、デザインしていくというのが設計の奥深いところだと思います。
今回はプレイヤー目線で、アコースティックギターでこだわりたい設計を3つだけについて考えてみましょう。
1 <丈夫さ>
”壊れにくさ””安定さ” とも言い換えられるかもしれません。
普通どんな製品も、丈夫なもの、壊れないものが良いとされています。
日本製の車や家電は素晴らしいですね。
でも楽器の世界ではより丈夫なものが一番良いかというと、、そうではないように思います。。
GREVEN グレーベン ギターです。
グレーベンが壊れにくい、丈夫なギターか、と言われると、そうではないかもしれません。
でも、、音は美しいのです。
アコースティックギターのレギュラーチューニングでは、トップに75kg ほどの張力がかかると言われています。
それで、ある程度の丈夫さが必要ですね。板を薄くしすぎればすぐ変形するかもしれません。
でもガチガチに作ってしまうと、振動を妨げてしまいます。
もちろん壊れたり、コンディションがあまりにも保てないと道具として使えないのですが、、。
丈夫さと振動を妨げないことは、反比例していますので、、バランスが難しいのです。
素晴らしいと感じるギターのほとんどはこの部分のバランスがとても良いのだと思います。
あくまで個人の感想なのですが、、どちらかというと、国産ギターは比較的丈夫さによっているような気もします。。
丈夫すぎて、音楽的な魅力を感じないギターが少なくないのかもしれません。
そのようなギターには大抵は、弦のテンションをしっかりかける調整をします。
そうすると「激なり」と錯覚する方もおられますが、、後述する音楽的な響き方とは少し違うのかもしれません。
コリングスやテイラーは、この辺りのバランスがとても良いギターだと思います。
特にプロの方など、演奏性にこだわりながら、ある程度音も良い楽器が欲しい方はかなり良い選択肢かもしれません。
2015年くらいのテイラー812です。
個人的には現在のVブレーシングより、この時期の音が好きなのでした。
ネックのコンディション、そしてネックに合わせたフレットの擦り合わせなどは、音に直結するので大切なのですが、
最近はネックアングルとフレットの擦り合わせがいかに音に影響するかも、知りました。
コリングスのネックの安定感は素晴らしいですね。
丈夫さを重視しますと、どうしてもネックがボルトジョイント、あるいは3ピースや5ピースなどになっていきます。
ボルトなどのパリッとした音がお好きな方もおられると思います。ただ少しキンキンとした音に聞こえてします。ワンピースネックでダブテイルジョイントのネックがフルに振動する感じとはやはり違います。
私個人はどちらかというとやはり、音楽的な響くギターが好きなのです。
それで丈夫さはもう少し捨てても、音が良いギターを選ぶ傾向があります。コリングスやテイラーよりももっと硬さがとれた楽器です。
もちろん、弾くたびに弦は緩めますし、ケースに保管し、湿度も管理しています。
「湿度管理までできません」という方もおられますが、そんなに難しくないと思います。
まずは少し良い湿度計を買って、部屋の湿度を知ることから始めてみるのはいかがでしょうか?
レッスンルームの加湿器です。
これまで、湿度管理しなくて悲惨な状態になったギターを何度も見ました。。
またギターは定期的なメンテナンスも必要ですね。
車に車検や定期メンテナンスが必要なのと同じですね。
ちょっとの管理で、十分に良いコンディションを保てると思います。
それなら、良い音で響く楽器の方が、断然ギターライフは楽しくなるともいます。
具体的なブランドについては、次の項目と重複しそうですので、少し後に書きたいと思います。
2 <ハーモニー>
ギターに限らず、最高峰と言われる楽器にはまずこの美しいハーモニーを出す力があります。
簡単に言いますと、実際に弾いた音以上の音を返す力のある楽器です。
試奏に来られた方は簡単な実験で、すぐに聞き分けられるようになります。
例えばレギュラーチューニングで6弦は「E音」ですね。82Hzです。
でもハーモニーがあるギターは、82Hzよりさらに低い音が反響してでます。
すぐに実験できます。
お持ちギターの6弦をしっかりと弾きます。
1秒後くらいにさらに低い周波数で「ズーン」と深い音が聞こえればハーモニーがあります。
こちらのグレーベンの音を聞いてみてください。
何度か聞いてみられても良いかもしれません。
わかる方にははっきりとわかると思います。本来弾いていない「ズーン」という低い周波数の音が聞こえます。
特に低音はオクターバーを使っているような感じがあるでしょうか。
(わからない方でも必ずピントが合う瞬間があります。
視覚も、ピントが合っていないと何かわかるようでボヤッとしているのですが、ピントが合うとはっきりわかりますね。
耳も、ハーモニーや後述する倍音などにピントが合う瞬間があります。)
これがコードになると何倍にも重なり合います。。
音の情報量が、とても多い感じです。
グレーベンは元々が柔らかい音色です。でも音色の傾向に関係なく、例えばもっと直線的な形のギターでも、同じくハーモニーがあるものはあります。
このようなハーモニーはギターのボイシングからくるものだと思います。
いわばトップを調律しているのです。
ギターの製作家が製作中のギターをタッピングしている様子を聞いたことがあるでしょうか??
GREVENさんと並んで、最高峰のルシアーと言われるソモジさんが製作中のギターをタッピングしている動画です。
太鼓のように「ボフッ ボフッ」という反響が聞こえますか?
ちなみにさらに高音の「カンッ」という音も素晴らしいですね。
このようなハーモニーがあるギターには何があるでしょうか??
全て上げることはできませんが、いくつか挙げてみましょう。
ご存知の通りマーチンは素晴らしいハーモニーですね。
低価格帯までしっかりとしたハーモニーがありますが、やはり18以上のランクで、素材が良いものは本当に美しいです。
こちらもスマホ録音ですが、D-18GE と HD28V です。
どちらもハーモニーを感じるでしょうか。
ギブソンやテイラーにもこのハーモニーがあります。コリングスもあります。
マーチン系のルシアーさんで、名高い方達のギター(メリル ジュリアスボージャスなどなど)素晴らしいハーモニーがあります。
マーチン系はかなり甘いサウンドです。
テイラーやローデンなどパリッとした音にもハーモニーがある楽器があります。
生徒さんがお持ちのローデンF50です。ローデンはなり方がかなり特殊です。
ローデンのあの音が好きな方にはたまらない楽器だと思います。
国産ギターはあまり網羅できていないのですが、、沖田さんが製作されたギターにもハーモニーを感じました。
単音は太くコードになるととろける感じですね。
ハイフレットまでデッドポイントなく響くギターで素晴らしい性能ですね。
沖田さんのギターが抜けてきたらかなりすごいかもしれません。
坂田さんのギターや岐阜で製作されているレゾナンスギターにもハーモニーを感じました。
ちなみにハーモニーを聞き分けるときの注意点は、「曲を聞かないこと」です。
これはスピーカーのテストと同じです。スピーカーのテストをするときに、流している曲が綺麗な曲か、は関係ありません。
音質に注目します。
同じように、ギターのテストをしていても、弾いているコードの種類がきれいかどうか、ではなく純粋に音色だけ聞いてみてください。
ハーモニーがある楽器は、ほとんどリバーブが要らないと感じます。
生なりが良いように思えても、レコーディングすると物足りず、リバーブやオクターバーを足したくなる場合、もしかしたら、ハーモニーが少し弱い楽器なのかもしれません。。
逆にハーモニーの豊かな楽器ですと、録音したときの立体感がすごいですね。
さてハーモニーにうるさくなると、さらに設計からくる「倍音」の魅力にお気づきになるかもしれません。
3 <倍音>
ここでいう倍音とは2倍音4倍音と呼ばれる上方向に上がっていく音のことです。
ピアノの鍵盤で言うと、
真ん中の「ド」 の音を弾くと、
オクターブ上の「ド」
さらにオクターブ上の「ド」 のことです。
この最初に弾く音を基音と言います。
この基音を弾いただけで、2倍音 4倍音を楽器が返してくるのです。
ストラトバリウスにはこの倍音があります。
単音ですが、コードのように上方向の音が鳴っているのが聞こえるのです。
ギターの世界でこの種の倍音が入っているのはかなり珍しいです。
一番有名なのはマーチンの40番代ですね。
この種の倍音が出るギターはほとんどありません。マーチン系の製作家でもごく一部のように思います。メリルやNGCの一部のモデルにもありますね。
グレーベンですとホワイトレディーにはこの種の倍音を強く感じます。
ご存知の方も多いかと思いますが、実は日本にこの分野ですごい方がおられます。
塩崎ギターの塩崎雅亮さんです。世界でも数少ない設計からくる倍音の構造を理解してギターを作り分けておられます。
倍音に関して興味があると言う方にはこちらの本がおすすめです。
D-45のムック本です。少し高額ですが、資料や読み物としても非常に参考になります。
塩崎さんの数ページにわたるインタビューだけでも読む価値があるかもしれません。。
先日新作のHLR-1 というギターを試奏させていただきました。エフェクタなしの録音ですが、倍音を感じられるでしょうか??
この種の倍音の立体さは特にコードをきれいに響かせたいという方にはおすすめです。
オクターブ上の倍音モデルと、ちょうどオクターブ奏法のように線も太くなります。
このブログでもよく登場するエアーズの最新作にもこの種の倍音がありますね。
生音の立体感がとても良いです。
おすすめのエアーズは色々ありますが、すでにローズ系の良いギターを持っておられる方なら、SJ04やSJ06など、マホガニーやメイプルのギターが面白いかもしれません。
倍音の入ったマホガニーやメイプルはかなり珍しいです。
これが本当に気持ちがよいです。
教室ホームページ:
https://sites.google.com/site/nacosticguitarschool/
教室ブログ(ギター、機材レポート):http://acouguist.blogspot.com
キューズランドミュージックスクール講師ページ:
http://www.qsland.jp/school/guitar/index.html#private_agfinger






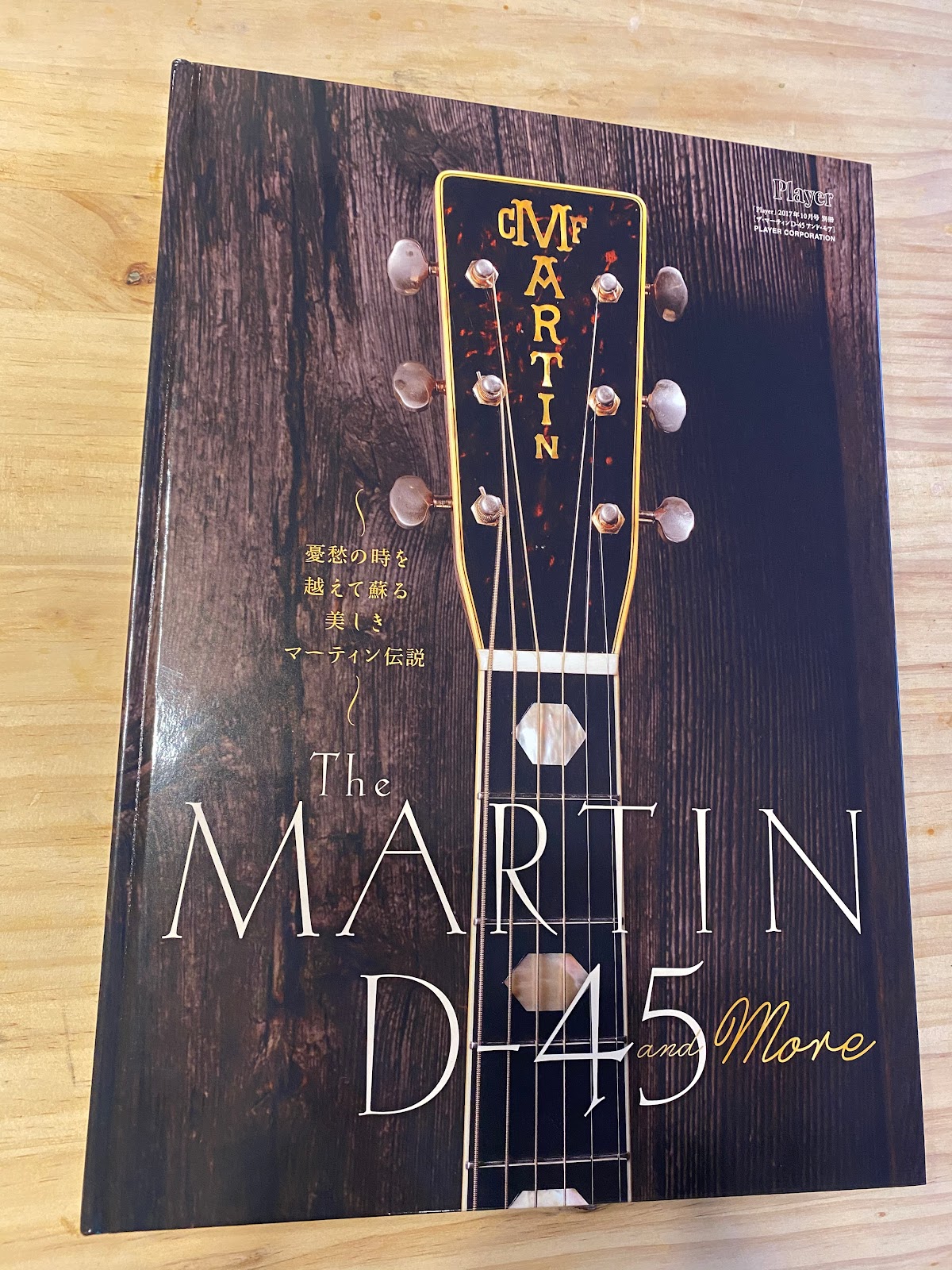

0 件のコメント:
コメントを投稿